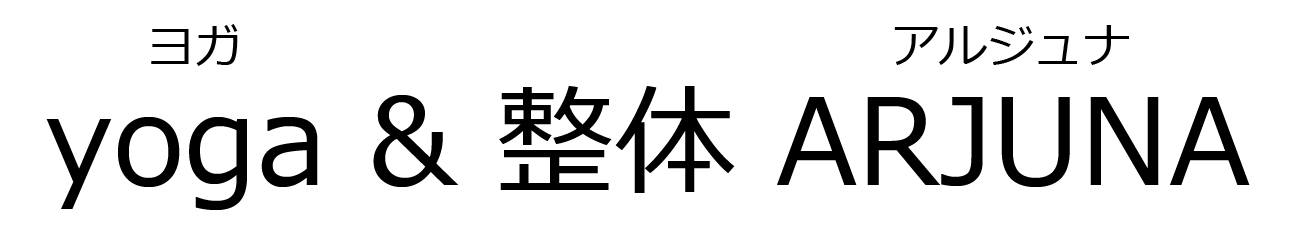ヨガがほかのエクササイズと一線を画すところってなんだろうか?
それは呼吸だろう。ヨガは呼吸を重要視する。
もちろん、ピラティスも呼吸は大事ですが、ヨガにおいては、アーサナ(ポーズ)よりも呼吸が重要で、さらにそれよりもっと瞑想が重要です。つまり「アーサナ」<「呼吸」<「瞑想」って感じ。

では、なぜ世間いっぱんにあるヨガ教室ではアーサナばかり練習しているのか。それは呼吸や瞑想は難しいからです。「えーっ、呼吸って生まれたときからやってるから難しくないよー」って思うかもしれません。それは呼吸の方法自体が難しいってのじゃなくて、呼吸の繊細さや効果をうけとることが難しいからなんだと思います。
だって、たとえば、呼吸だけのクラスがあったとして、そんなクラスにみなさんは参加したいって思いますか?退屈でツマラナイって思うでしょ?そんな退屈なクラスにお金や時間をかけるのすら勿体ないみたいな。
それ、普通の感覚です(笑)
ふつうのひとは、呼吸に10分も集中することなんてできない。
だから、アーサナから入ります。
アーサナは呼吸にくらべて感覚的な刺激があるからつづきます。効果もうけとりやすい。
無味の水は飲み続けられませんが、コーラやビールだったら甘い味やノドごしがあるから飲み続けられれますよね(笑)

まぁ、このように、呼吸に比べてアーサナは難しくないとはいっても、それでも簡単ではなく、人によってはアーサナの繊細さや効果を感じきれないひとも多くいると思います。
ヨガの先生によってはアーサナ中に呼吸のインストラクションをいれている先生もいるし、アシュタンガヨガではヴィンヤサ(動きと呼吸を連動させる)をいれているので、ちゃんと呼吸の練習もやってるって感があるかもしれないけど、初心者にそれは難しいと思います。ただでさえ、呼吸はアーサナより難しいのに、難しいアーサナと難しい呼吸を一緒にすることは、逆にヨガから遠ざかり、ヨガ迷子になっちゃうのかなーって思います。
もし、それ(アーサナと呼吸を同時にできること)を最初からできるようなら、その人は、わりとひとかどのひとです。ヨガをやらなくてもだいたい心も身体も整っているひとだし、おそらく、ヨガ偏差値が60以上はあるでしょう。
でも、世の中、そんな整っている人ばかりではない。
そうではなく、偏差値40~59の人でも、幸せになれるようにするのがヨガなのかなって思います。だから、普通の人はアーサナはアーサナだけで、呼吸は呼吸だけで別々に練習するのが良いと思います。最初からアシュタンガヨガみたいな、いっぺんに複数のテクニックに注意が向き、それを持続することができるようなひとは、すでにひとかどのひと。平均はもっと下にあります。

そもそも「呼吸」とは、酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する生理現象です。でも、みんなはもっと簡単なイメージを持っていることだろうと思います。それは「鼻や口から空気を吸って、鼻や口から吐き出す」ってやつ。ここまでの人は呼吸が非常に浅い。呼吸のイメージも浅い。もし、ヨガで呼吸方面をもっと頑張りたいと思うなら、呼吸のイメージや概念を拡げていきましょう。
肺まで入れいている感覚ってありますか?最低でも、ヨガをやったら肺までは空気を入れているイメージを持った方がいいでしょう。
つぎなるイメージは酸素が肺胞から血液に取り込まれ、ヘモグロビンが酸素を受け取って全身の血流としてまわっているイメージを持ちましょう。ここまでくると生理学的で具体的なイメージですが、プラーナや気、ナーディなど抽象的な概念でイメージにするともっとヨガが捗るかもしれません。
ですが、ただ、酸素が体中をめぐっているだけでは何の役にも立ってません。ここからさらに、全身をまわっているヘモグロビンは各臓器や組織の細胞で酸素を手放して、細胞内にはいります。細胞にはいろいろな種類があります。筋細胞であったり、神経細胞であったり、肝細胞、膵細胞、多種多様な細胞があります。そのなかにあるミトコンドリアという小さな場所で脂質や糖質から酸素の酸化という力を利用して、ATPというエネルギーが取り出されます。私たちの身体は、このATPというエネルギー通貨を利用して動いています。その過程で、二酸化炭素と水が取り出され、さっきと逆の流れをたどって肺から大気中に排出されます。
呼吸の練習でそこまでイメージすることができたなら、全身の細胞からエネルギーが湧いてくるのがわかるかもしれません。ここまでくると瞑想の一種となるでしょう。
でも、この呼吸のイメージは呼吸のエネルギーの側面です。酸素や二酸化炭素、温度は体の至る所にある様々な種類のセンサーを刺激し脳にデータを送ります。そして、そのデータに対しての結果をそれぞれの各臓器に送り返します。そのやりとりは自律神経である交感神経と副交感神経を通じて行われます。これまた解剖生理のはなしは複雑すぎて瞑想の邪魔をしてしまうので、次のように抽象化してしまいましょう。交感神経は「ピンガラー」という気の経路にして背骨の右側にイメージし、副交感神経は「イダー」という気の経路にして背骨の左側にイメージして呼吸します。イメージしやすいように具体的には左右の鼻の穴を使います。
ここまで呼吸のイメージを抽象化して概念を拡げることができたなら、自律神経が整っていき、体の不調が改善され、エネルギーに充ち溢れていくことでしょう。
随分と呼吸だけの練習を継続し、イメージが十分馴染んでくるころには、だんだんと呼吸の回数が減っていきます。ふつう1分間に15回くらいだったのが、だんだん10回以下になってきます。できれば4~6回くらいを目指します。1分間あたりの回数が減るってことは1回の呼吸が長くなるか、または吐いてもなく吸ってもない止まった時間が長くなるかだと思います。ということは一呼吸が15秒くらいでしょうか。
ここまできて、やっと、他人の呼吸のインストラクションにあわせることができるようになります。たとえば「吸う息で〇〇、吐く息で〇〇」みたいなインストラクションです。これも先生によって、呼吸のタイミングや長さが違います。
初心者に多い、呼吸数が早くて短いひとは、ポーズの一挙一動にあわせた呼吸のインストラクションについていけないと思います。むりに合わせると逆に苦しくて心地よくないヨガになっちゃって本末転倒です。安静時呼吸が15回/分としてもアーサナ中だからもっと早くて20回/分だとします。すると一呼吸が3秒です。吸う息1.5秒、吐く息1.5秒と換算しても、いやに忙しないバタバタとしたポーズの流れ(フローヨガ)になっちゃいます。
呼吸ってみんな人それぞれで、心地よいと感じる呼吸の長さやタイミングが違うのに、一人の先生が、心地よいと感じる長さやタイミングを押し付けたインストラクションは苦しいだけ。呼吸の短い人は、長い人に合わせることができない。
でも、その逆は大丈夫です。呼吸の長い人は短い人にあわせることができます。心地よいかは別として。
なので、先生は呼吸の長さがある程度そろったグループに対しては、ヴィンヤサのインストラクションを行ってもいいけど、そうでないなら、アーサナと呼吸法の練習を分ける必要がある。また、生徒は呼吸法の練習を十分やって呼吸の繊細さを十分感じ取ることができるようになってからアーサナと連動させると良いと思う。平均的な生徒はね。
すでに身体能力が高くて、偏差値60以上のひとは最初からアーサナと呼吸を連動させてもいいとは思うけど、そんなひとはヨガの能力が正規分布しているとしても16%くらいしかいません。40人クラスがあったとして6人くらい。
ヨガでは所詮、アーサナや呼吸というのは、瞑想への準備という位置づけです。最初にも言ったように、瞑想は難しいから、もっと簡単な呼吸から。それでも呼吸が難しい人はアーサナからやるってのがヨガの流れ。
最初から瞑想できるならアーサナや呼吸をすっ飛ばして瞑想やるってのが仏教かな。そのてん、ヨガは親切ですよね。

まぁ、これは時代のせいであるかもしれない。この現代的で都会的な生活様式では、昔みたいに直接、瞑想から入るのは難しい。昔は、家電製品や車なんかの便利な道具がなかったから、もっと人間の身体能力が高くてアーサナする必要なかっただろうし、自然の多いところや田舎ではボーっとする時間や、畑仕事や家事仕事で繰り返し作業が多かったら日常生活が瞑想的であった。
昔のひとは、そういうアーサナ的な身体感覚と、自律神経(呼吸と心)が整うような環境がすでにあった。だから、もう瞑想に直接入るための準備ができていたんだと思います。
でも、今は違う。テレビやスマホ、SNSのおかげで人心も乱れ、ストレスフルな時代。便利な家電や、甘いもの、刺激的なものがたくさんあるし、刹那的で快楽的なものにあふれかえっている。化石燃料と飛行機をつかえば地球の裏側へひとっとびで、インドに行ったり、ボランティアやったり、やりたいことがなんでもできる。そしてそれを自己探求だとか自己実現だとかと思って、すばらしいことだと勘違いしている。幻想である。
ヨガは外側に自己や幸せを求めない。
忙しくて時間がないから、アーサナと呼吸、瞑想をいっぺんにやるっていうアシュタンガみたいなヨガは効率的で現代的だなーとも思う。時代の要請に応えるかたちで世界的に流行ってるんだろうな。
それでも、アーサナはアーサナで、呼吸は呼吸で、副次的な効果があるから、身体的で現世利益的な効果を得たい人は、アーサナと呼吸を頑張ったらいいと思う。